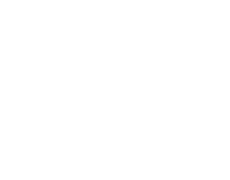2024年度 研究会開催記録
◎第91回定例研究会(ハイブリッド開催)
日時:2024年 7月 13日(土)14:00-17:00
場所:桐朋学園大学 調布校舎 C008室、およびオンライン
司会:朝山 奈津子(弘前大学)
内容:修士論文発表4件
1.狂言歌謡「小舞謡」の音楽的特徴について
――山本東次郎家の伝承を例に――
小林 雪乃(武蔵野音楽大学大学院)
2.ピアノ協奏曲におけるカデンツァの演奏
――ベートーヴェン《ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調》Op.15 第1楽章を例に――
嶋岡 敦子(一橋大学大学院)
マルセル・デュプレによるオルガン奏法のアプローチと彼の美学
発表言語:日本語
4.基礎的な和声の学習における諸問題に対する認知科学的考察
――ピアノの演奏技能に関する問題を中心として――
唐津 裕貴(東京藝術大学大学院)
◎第90回定例研究会(ハイブリッド開催)
日時:2024年 6月 8日(土)14:00-17:00
場所:昭和音楽大学 南校舎 A214教室
司会:早稲田 みな子(国立音楽大学)
内容:修士論文発表5件
1.越後瞽女唄の伝承とアイデンティティの様相
――現在の演奏活動に至るまでの変化に焦点を当てて――
齋藤 穂歌(東京藝術大学大学院)
2.モーリス・ドラージュ《7つの俳諧》(1923)
――「他者」からの影響で見出した音楽的簡素さ――
秋道 瑠香(青山学院大学大学院)
3.19世紀後半プラハにおける「チェコ音楽史」構築の経緯
――オタカル・ホスチンスキーの議論を中心に――
髙宮 理彩子(東京藝術大学大学院)
4.ヨハネス・ブラームス《8つのピアノ小品》作品76より第7番「間奏曲」の分析
池田 和音(お茶の水女子大学大学院)
5.早坂文雄の「美」をめぐる言説 ――「日本的なもの」への視点を通して――
山本 香紫(東京音楽大学大学院)
◎第89回定例研究会(ハイブリッド開催)
日時:2024年 5月 11日(土)14:00-17:00
場所:昭和音楽大学 南校舎 A214教室
司会:中田 朱美(国立音楽大学)
内容:卒業論文発表1件、修士論文発表4件
卒業論文発表
1.武満徹と〈日本的なもの〉 ――第二次世界大戦前後の日本音楽と西洋――
那須 晴樹(東京大学)
修士論文発表
1.ピエール・ブーレーズの初期セリー作品における音楽論の反映
――作品分析から紐解かれる音楽哲学と方法論――
山本 真幸 (東京藝術大学大学院)
2.ブルガリア民俗音楽における「伝統」の継承と発展
――楽器と教育のトラキア化とソヴィエト化に着目して――
玉置 彩乃(東京藝術大学大学院)
3.モーツァルトのピアノ協奏曲におけるピアノ・リダクションの考察
菊間 倫也(東京藝術大学大学院)
4.ハンス・ロット《弦楽四重奏曲 ハ短調》(1876-1877)
――史料と作曲技法が示唆する「4楽章」構想――
山崎 圭資(青山学院大学大学院)
2023年度 研究会開催記録
◎第87回定例研究会(ハイブリッド開催)
日時:2024年 3月 25日(月)14:00-16:00
場所:国立音楽大学 新1号館 合唱スタジオ(N-128)
企画・講演・演奏:青柳 いづみこ(大阪音楽大学名誉教授)
司会:中田 朱美(国立音楽大学)
内容:演奏付き講演
パリのサロンで生まれた音楽 ――19世紀末から1920年代まで――
共演:飯島 聡史(国立音楽大学大学院助教)
資料作成・発表補佐:石野 香奈子(明治学院大学大学院)
演奏曲目
1.グレフュール伯爵夫人のサロンから
ガブリエル・フォーレ:パヴァーヌ op.50(1886)(ベンフェルドによる4手連弾版) [★☆]
2.マドレーヌ・ルメールのサロンから
レイナルド・アーン:画家の肖像 プルーストの詩による(1907)
2)パウルス・ポッテル 3)アントニー・ヴァン・ダイク [☆]
3.サン=マルソー夫人のサロンから
フォーレ=メサジェ:バイロイトの思い出
〜カドリール風幻想曲 ワーグナー『ニーベルングの指輪』のテーマによる [連弾 ★☆]
4.ポリニャック大公妃のサロンから
エリック・サティ:交響的ドラマ『ソクラテス』(1918)
第1部 ソクラテスの肖像(ジョン・ケージによる2台ピアノ版) [☆★]
5.ユイガンス音楽堂から
ジェルメーヌ・タイユフェール:野外遊戯 から 第1曲 ティルリタンテーヌ [2台ピアノ ★☆]
6.ヴィユ・コロンビエ座から
ルイ・デュレ:カリヨン(1916) [連弾 ☆★]
7.ミヨーの土曜会から
ジョルジュ・オーリック:さらばニューヨーク!(1920)
(ダリウス・ミヨーによる4手連弾版) [☆★]
◎第88回定例研究会(ハイブリッド開催)
日時:2024年 3月 23日(土)14:00-17:00
場所:福島大学 音楽棟 311(合奏室)
司会:杉田 政夫(福島大学)
内容:個人研究発表2件
1.ヴァイオリンとライヴ・エレクトロニクスのための作品委嘱を通した研究
2.A. ヴィルヘルミのJ. S. バッハ《シャコンヌ》校訂編曲にみる19-20世紀のヴァイオリニストの系譜
横島 浩(福島大学) ※ゲスト奏者 横島 礼理(NHK交響楽団)
朝山 奈津子(弘前大学)
◎第86回定例研究会(ハイブリッド開催)
日時:2024年 1月 20日(土)14:00-17:00
場所:桐朋学園大学 調布校舎 C008
司会:安田 和信(桐朋学園大学)
内容:樋口 隆一先生講演会(研究会運営委員会企画)
『新バッハ全集』とわたしの音楽活動
◎第85回定例研究会(ハイブリッド開催)
日時:2023年 12月 16日(土)14:00-17:00
場所:東京藝術大学上野校地 音楽学部 5-301
司会:朝山 奈津子(弘前大学)
内容:研究発表3件
1.ローマ大賞受賞者としてのG. ビゼーのオペラ創作
――19世紀フランスにおけるローマ賞の支援制度――
落合 美聡(東日本支部)
2.ビデオゲーム・プレイと音楽的行為
――Ludomusicologyにおける「ミュージッキング」概念の展開について――
山上 揚平(東京大学)
3.ガルス・ドレスラーの初期詩篇モテット曲集に関する研究
――成立背景と作曲技法を中心に――
大角 欣矢(東京藝術大学)
◎特別研究会(ハイブリッド開催)
日時:2023年 8月 14日(月)14:00-17:00
場所:国際基督教大学 本館4階 宗教音楽センター内 音楽ホール
共催:国際基督教大学宗教音楽センター
司会・通訳:佐藤 望(国際基督教大学)
内容:バッハ資料研究の現在について 講演会
講演者:クリスティーネ・ブランケン博士
(ライプツィヒ・バッハ資料財団上級研究員、ライプツィヒ大学講師)
講演題目:今日のバッハ研究:問題と展望
◎第84回定例研究会(ハイブリッド開催)
日時:2023年 7月 8日(土)13:30-17:00
場所:国立音楽大学 5号館121教室
司会:朝山 奈津子(弘前大学)
内容:研究発表4件
1.言説から見るハインリヒ・マルシュナー
――《ハンス・ハイリング》の成立に関する書簡を中心に――
由上 渓子(東日本支部)
2.クロード・ドビュッシーと「月lune」 ――「月lune」の音楽表現とその変遷――
高徳 眞理(国立音楽大学大学院)
3.バルトーク作曲《ピアノ・ソナタ》BB88第3楽章における「フルヤ」の装飾
――民俗音楽の「模倣」から「醸出」への試み――
木村 優希(お茶の水女子大学大学院)
4.コレッリ《ヴァイオリン・ソナタ集》作品5における装飾法の考察
――現代における演奏指針としての装飾パターンの原則――
堀内 由紀(桜美林大学)
◎第83回定例研究会(ハイブリッド開催)
日時:2023年 6月 17日(土)14:00-17:00
場所:国立音楽大学 6号館101教室およびオンライン
司会:石川 亮子(昭和音楽大学)
内容:修士論文発表 4件
1.芥川也寸志の《エローラ交響曲》(1958)の分析
――男性楽章・女性楽章の書き分けと楽章間の結びつきに着目して――
阪内 佑利華(お茶の水女子大大学院)
2.道化・鏡・鈴 ――「グロテスク」から見るオペラ《こびと》《烙印を押された人々》――
小野寺 彩音(東京藝術大学大学院)
3.オリヴィエ・メシアンの「移高の限られた旋法」再考 ――1930年代の作品を中心に――
植村 遼平(慶應義塾大学大学院)
4.ハンス・ロットの目指した音楽
――《田園的前奏曲》を中心とする器楽作品におけるフーガについての論考――
村上 功一(東京大学大学院)
◎第82回定例研究会(ハイブリッド開催)
日時:2023年 5月 13日(土)14:00-17:00
場所:国立音楽大学 5号館121教室およびオンライン
司会:安田 和信(桐朋学園大学)
内容:修士論文発表 4件
1.17世紀後半から18世紀前半にかけてのリコーダーとフルートの編曲文化
――パリとロンドンの音楽愛好家の活動を中心に――
井上 玲(東京藝術大学大学院)
2.1920〜30年代の新民謡運動における「民謡」再考
――作曲家の創作理念と活動にみる「国民性」の発見と表出をめぐって――
長谷川 由依(東京藝術大学大学院)
3.パーシー・シェリーの詩作品と付曲の比較検討 ――「愛」を歌った晩年の抒情詩を中心に――
内藤 瑠梨(東京藝術大学大学院)
4.明治から戦前期の日本民衆歌における伴奏の変遷と機能和声聴取の普及
――1930年代の古賀政男作品における日本的伴奏の試みと日本的歌唱法への移行に注目して――
山本 茉輝(東京大学大学院)